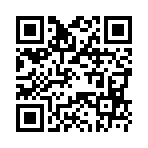2011年05月10日
GWまとめ3
前からやろうやろうと思っていたことなんですが、今回はローラーの改造です。
ローラーを滑らすにはステンとの摩擦を減らせばよいが、同時にラインとの摩擦も減ってしまう。
ということはローラーが回っているのではなく、滑っているってことになるとラインの状況(ゴミ付着)などにより、進みにくくなってしまうと思う。
ラインとローラーの接地面の摩擦を上げることで、すべりをコントロールしやすくできるのではないかということで改造してみました。
今使っているローラーはステンとの摩擦はかなり少ない。(ちょっとした構造になっているので)
けど、ラインとの接地面はプラスチックでラインは滑りやすい。
そこで、接地面の摩擦を上げるために熱収縮チューブを取り付けてみた。

糸掛け部はのんきやえんとそっくりです。
ちっちゃなこだわりは何箇所かありますが。
ラインを通して比較すると、ローラーが回っている感がかなり伝わってくる。
それと、支柱との距離、ローラーの孔径と支柱径の関係なのですが、
進むときはスムーズで戻るときはブレーキが掛かります。
ローラーの孔系がφ1.5mmに対し、支柱径はφ1.0。
どうやら戻るときは支柱側にローラーがずれて回転し、支柱に接触しているようです。
ただし、この状態は狙って作れるものでなく、偶然できたものでした(笑
まだ、実戦投入してませんが、だめだったらすぐに取れるんで問題ないでしょうww
もう一個秘密兵器(たいしたものではありませんが・・・)を準備して3キロアップ用の準備は完了です。
今週は台風一号の影響が出るかどうか。。。
まぁ関係なくいっちゃうんでしょうが(笑
ローラーを滑らすにはステンとの摩擦を減らせばよいが、同時にラインとの摩擦も減ってしまう。
ということはローラーが回っているのではなく、滑っているってことになるとラインの状況(ゴミ付着)などにより、進みにくくなってしまうと思う。
ラインとローラーの接地面の摩擦を上げることで、すべりをコントロールしやすくできるのではないかということで改造してみました。
今使っているローラーはステンとの摩擦はかなり少ない。(ちょっとした構造になっているので)
けど、ラインとの接地面はプラスチックでラインは滑りやすい。
そこで、接地面の摩擦を上げるために熱収縮チューブを取り付けてみた。
糸掛け部はのんきやえんとそっくりです。
ちっちゃなこだわりは何箇所かありますが。
ラインを通して比較すると、ローラーが回っている感がかなり伝わってくる。
それと、支柱との距離、ローラーの孔径と支柱径の関係なのですが、
進むときはスムーズで戻るときはブレーキが掛かります。
ローラーの孔系がφ1.5mmに対し、支柱径はφ1.0。
どうやら戻るときは支柱側にローラーがずれて回転し、支柱に接触しているようです。
ただし、この状態は狙って作れるものでなく、偶然できたものでした(笑
まだ、実戦投入してませんが、だめだったらすぐに取れるんで問題ないでしょうww
もう一個秘密兵器(たいしたものではありませんが・・・)を準備して3キロアップ用の準備は完了です。
今週は台風一号の影響が出るかどうか。。。
まぁ関係なくいっちゃうんでしょうが(笑
Posted by マーブー at 07:01│Comments(2)
この記事へのコメント
ヤエン人さん、はじめまして!
ヤエンが外套膜の表側(甲)に掛かる件についての私見です。
的外れかもしれませんので、心当たりがなければ読み流してください。
すでにご存知のとおり、ハリ掛かりしたアオリが逃げる様は、まさに膨らませた風船を放ったときのような動きをします。この際にすでに違う場所に軽くハリ掛かりしていたヤエンが、甲側に掛かり直すことがあります。しかしその確率はあまり高くなく、1回の釣行で何度も起こるというものではありません。
自作ヤエンの写真を拝見する限りでは、おそらく前脚と後脚のバランスによるものではないかと思います。ヤエンは「前上がり・前下がり」のバランスも重要ですが、「前脚の高さ」、「両脚の長さの差」、「両脚の間隔」が非常に重要な要素となります。
ラインが一直線で、ヤエンがアオリの真下に入るケースが理想ですが、かなりハリハリにテンションを掛けても、アオリが走ったり潮でラインが吹けるのは経験的におわかりになるでしょう。このケースにおいて「両脚の長さの差」が大きいと、大げさに言うと到達時にアオリよりハリが上にきている可能性があります。この状態でアワセを入れると、ハリが甲側にフッキングすることがあります。
これらを検証するためには、まずは後脚の長さを短くして、ハリが外套膜内に突き刺さるくらいまで調整してみてください。ヤエン人さんの自作ヤエンであれば、「両脚の間隔」が広がりますが、後脚を後方に倒すのも一法かと思います。そこから両脚のバランス、そして両脚の間隔を調整されたらよいと思います。ヤエンの調整を始めると必ず掛け率が下がりますが、ご興味があれば試行錯誤してみてください。
ヤエンが外套膜の表側(甲)に掛かる件についての私見です。
的外れかもしれませんので、心当たりがなければ読み流してください。
すでにご存知のとおり、ハリ掛かりしたアオリが逃げる様は、まさに膨らませた風船を放ったときのような動きをします。この際にすでに違う場所に軽くハリ掛かりしていたヤエンが、甲側に掛かり直すことがあります。しかしその確率はあまり高くなく、1回の釣行で何度も起こるというものではありません。
自作ヤエンの写真を拝見する限りでは、おそらく前脚と後脚のバランスによるものではないかと思います。ヤエンは「前上がり・前下がり」のバランスも重要ですが、「前脚の高さ」、「両脚の長さの差」、「両脚の間隔」が非常に重要な要素となります。
ラインが一直線で、ヤエンがアオリの真下に入るケースが理想ですが、かなりハリハリにテンションを掛けても、アオリが走ったり潮でラインが吹けるのは経験的におわかりになるでしょう。このケースにおいて「両脚の長さの差」が大きいと、大げさに言うと到達時にアオリよりハリが上にきている可能性があります。この状態でアワセを入れると、ハリが甲側にフッキングすることがあります。
これらを検証するためには、まずは後脚の長さを短くして、ハリが外套膜内に突き刺さるくらいまで調整してみてください。ヤエン人さんの自作ヤエンであれば、「両脚の間隔」が広がりますが、後脚を後方に倒すのも一法かと思います。そこから両脚のバランス、そして両脚の間隔を調整されたらよいと思います。ヤエンの調整を始めると必ず掛け率が下がりますが、ご興味があれば試行錯誤してみてください。
Posted by アオリスト at 2011年05月10日 20:49
アオリストさん
はじめまして!
貴重なコメントありがとうございます。
針が上になって届くことがあるんですね。
いままでがまかつのヤエンとか下側に針が付いていてなんでだろうって思っていましたが、こういうケースのためなんですね。
マイヤエンはのんきやえんのLLサイズを参考につくりました。
ただ、針先が垂れてしまうので、後ろの支柱を10mm長い位置にしてあります。
最終的にラインを通したときに先端の針先とラインとの距離が10mmくらいを目安に仕上げています。
後ろの支柱を低くすると針とラインとの距離が広くなりすぎてしまうと思うので、前の支柱も短くして検証してみます!
ありがとうございました!
はじめまして!
貴重なコメントありがとうございます。
針が上になって届くことがあるんですね。
いままでがまかつのヤエンとか下側に針が付いていてなんでだろうって思っていましたが、こういうケースのためなんですね。
マイヤエンはのんきやえんのLLサイズを参考につくりました。
ただ、針先が垂れてしまうので、後ろの支柱を10mm長い位置にしてあります。
最終的にラインを通したときに先端の針先とラインとの距離が10mmくらいを目安に仕上げています。
後ろの支柱を低くすると針とラインとの距離が広くなりすぎてしまうと思うので、前の支柱も短くして検証してみます!
ありがとうございました!
Posted by マーブー at 2011年05月11日 07:49
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。